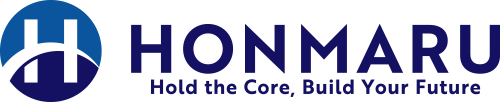はじめに
この記事は約7分で読めます。
事業を成長させるうえで、必要な資金をどう調達するかは経営者にとって常に大きなテーマです。
とくに、運送業や倉庫業、建設業、製造業、卸売業、不動産業など、設備投資や多額の運転資金が必要な業種の経営者の方は「安定的に資金を調達できる方法」を模索しているかもしれません。
また、スタートアップ企業の創業期・成長期でもまとまった資金が必要になるケースがあり、「融資と出資、どちらが有利なのだろう?」と悩むこともあるでしょう。
「融資」と「出資」は、いずれも資金調達の手段として一般的に用いられますが、それぞれのメリット・デメリットや注意点、資金を受ける際のプロセスなどは大きく異なります。
そこで今回は「融資と出資の違いは何?」というテーマを掘り下げながら、成功のポイントや最大の注意点について詳しく解説していきます。
記事を理解し、事業内容や状況に応じてどちらを選ぶべきか、あるいは両方をうまく組み合わせるべきかを検討することで、効果的な資金調達計画を立てることができるでしょう。
ぜひ、これからの経営に役立ててください。
- 融資と出資の最も大きな違い
「返済義務の有無」と「経営権をどの程度手放すか」 - 融資の特徴
返済義務がある代わりに、経営権を維持しやすい - 出資の特徴
返済義務がない一方で、経営権の一部を譲渡する必要がある点が重要 - どちらを選択するか
運送業や建設業、製造業、不動産業など設備資金ニーズの高い業種、またスタートアップ企業などにとって、どちらの手段を選ぶかは事業戦略と深く関わる - 資金調達を成功させるためには
事業計画書や資金繰り表をしっかりと作り込み、金融機関や投資家とのコミュニケーションを丁寧に行うことがポイント
元銀行員×融資審査の中枢にて2,000社以上の企業融資を担当してきたプロが、融資調達のサポートします。
特に1,000万円〜数億円規模の高額融資調達に強みを持ち、豊富な経験と知識を活かして、銀行との交渉や資料作成をサポート。
スムーズに、より好条件の融資調達を果たします。
融資と出資の違いは何?
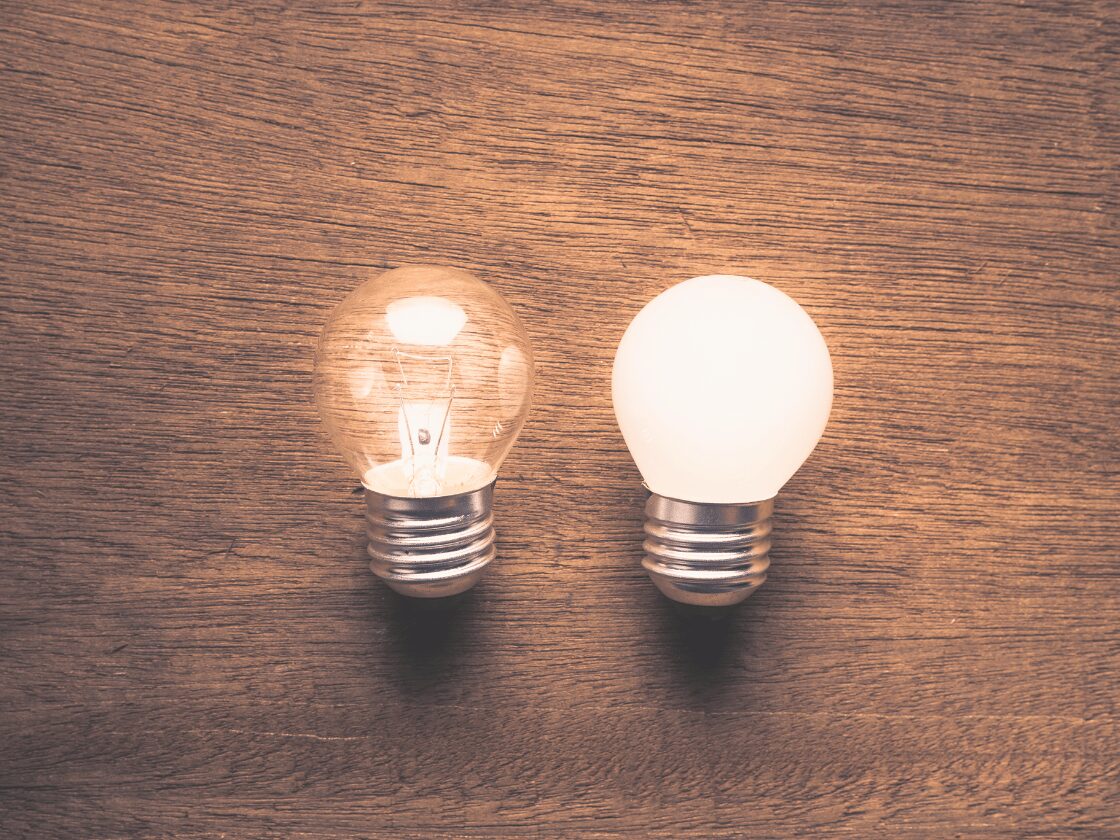
資金調達の代表的な方法として挙げられる「融資」と「出資」ですが、両者には根本的な違いがあります。
最も大きな違いはお金を返済する義務があるかどうかです。
- 融資: お金を借りる行為。借りたお金(元本)を利息とともに返済する義務がある。
- 出資: お金を出してもらう行為。原則として返済義務はなく、代わりに出資者に株式や持分を提供して経営権の一部を譲渡する。
このほかにも、資金提供者の立場が異なることも大きいポイントです。
融資の場合は、銀行や信用金庫など金融機関が主な提供者となり、返済を前提とした関係になるのが一般的です。
一方、出資の場合はベンチャーキャピタル(VC)やエンジェル投資家、時には事業パートナーや親会社など、より経営に深く関与し、成長に寄与することを目的として資金を提供してくれます。
なぜこの違いを理解する必要があるのか?
経営者にとっては、どの資金調達手段を選ぶかによって、事業の進め方や経営方針が大きく変わります。
銀行融資を受ける場合は、返済スケジュールを守りながら、金融機関が求める一定の財務健全性を確保していくことが重要です。
一方、出資を受ける場合は、出資者とのコミュニケーションや経営方針の共有が極めて重要になり、場合によっては意思決定のスピードや方向性にも影響が及びます。
また、短期的な資金ニーズなのか、長期的な成長資金なのかといった、調達の目的によっても向き・不向きが変わるため、「融資」と「出資」の違いを正しく理解しておくことが欠かせません。
「融資」と「出資」どちらがいい?
- 中小企業庁が公表した「2024年版中小企業白書」では、中小企業が成長に向けた設備投資における、外部からの資金調達手段として「融資」を利用している割合は約64%に上るとのデータがあります。次点に「自己資金」で投資を実施した割合は約27%でした。
- 一方で、出資(エクイティファイナンスや親会社・関係会社からの借入)による資金調達はまだまだ一般的ではなく、割合は約3%でした。
※参考:
中小企業庁「2024年版中小企業白書」P.6
中小企業庁HP
日本の中小企業・中堅企業にとっては、まず融資を検討するケースが圧倒的に多いといえます。
しかし、スタートアップ企業の先行投資や研究開発など、リターンが得られるまでに時間のかかるプロジェクトでは、返済義務のある融資だけでは難しい場面もあるでしょう。
このような場合に「出資」という選択肢を検討する意義が生まれます。
融資の3つの特徴
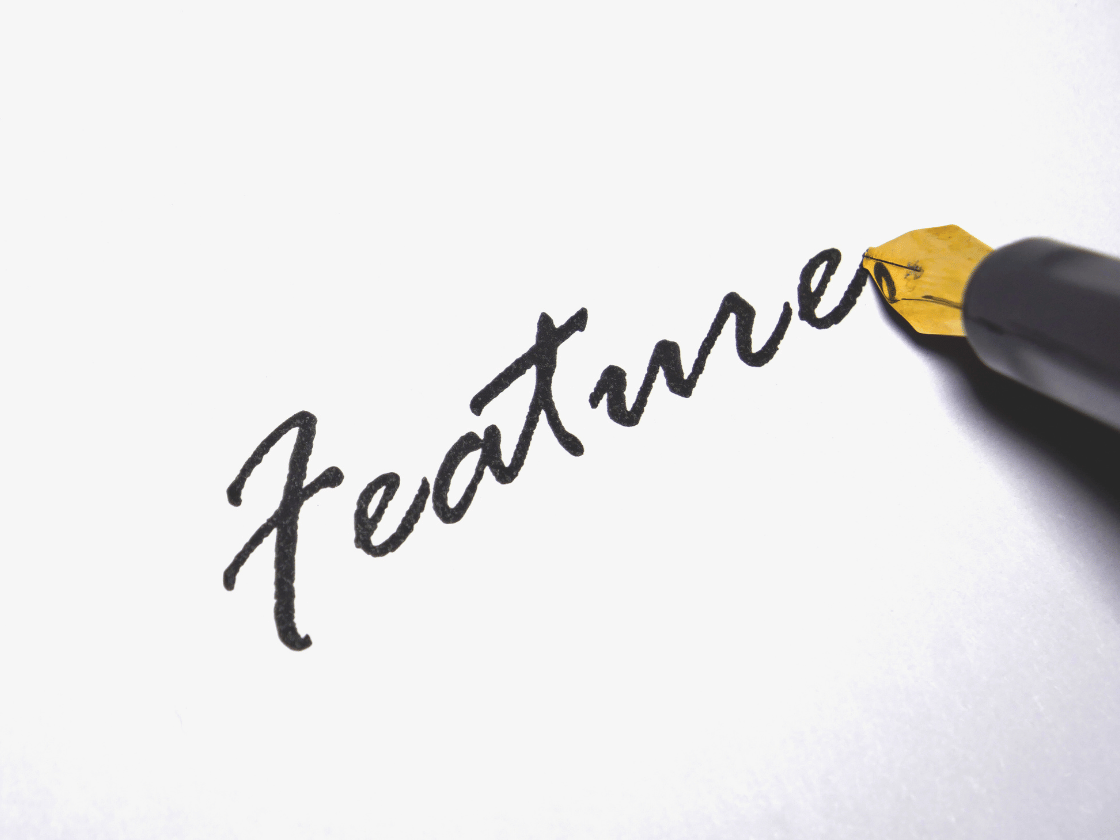
1. 返済義務がある
融資の最大の特徴は、先ほども述べたとおり返済義務があることです。
借りたお金(元本)に加えて利息も支払わなければならないため、事業計画上、毎月または一定期間ごとの返済負担を考慮しなければなりません。
業種によっては売上や入金のタイミングが読みにくい場合があります。
返済が滞るリスクも念頭に置く必要があるため、資金繰り計画は綿密に行わなければいけません。
2. 経営権を手放す必要はない
融資を受けても、金融機関から経営権を譲渡する必要はありません。
外部の干渉をできるだけ抑えたい場合には、大きなメリットとなります。
とくに、創業者やオーナー経営者にとって、「会社を自分の意思で運営し続けたい」という考え方は重要でしょう。
ただし、融資を継続的に受けるためには、金融機関との信頼関係の構築が欠かせません。
決算書の内容や事業計画の実行状況などをきちんと報告し、返済能力を示すことで、追加融資や増額に繋がっていくこともあります。
3. 比較的安定した調達ができる場合が多い
条件さえ整えば、金融機関の融資枠内での調達は比較的安定しやすいといえます。
金利水準も、ベンチャーキャピタルなどからの出資と比べて「コスト」が明確に見えやすいのが特徴です。
ただし、金融機関は事業の安定性や財務状況を重視するため、設備資金や運転資金を貸し出す際には、担保や保証などを求められる可能性があります。
また、新規事業やスタートアップの場合は、実績や信用力が不足していることから、思ったように融資を受けられないこともあるでしょう。
出資の3つの特徴

1. 返済義務は基本的にない
出資金は借金ではないため、原則として返済義務がありません。
その代わりに出資者には株式(株主)や持分(出資者)を取得してもらう形が多いです。
事業が順調に成長すれば、出資者は株式の値上がり益や配当などを通じてリターンを得ることができます。
返済の重荷から解放されるという意味で、資金繰りが厳しくなりがちな創業期や拡大期のスタートアップ企業にとっては魅力的な資金調達方法です。
大きな資金を呼び込める可能性がある一方、次に挙げるような注意点も存在します。
2. 経営に口出しされる可能性がある
出資者は株式や経営権を取得するため、会社の重要事項に対して発言権や veto(拒否権)を持つ場合があります。
とくにベンチャーキャピタルや戦略投資家などは、資金を提供するだけでなく、経営方針や人事、提携戦略などにも深く関与することがあります。
スタートアップや中小企業にとっては、出資者からのネットワーク・ノウハウ提供がプラスに働く場合も多いですが、経営の自由度が低下するリスクもあるため、経営者のマインドセットやビジョンにマッチする投資家を選ぶことが重要です。
3. 株式を渡すため、将来的にリスクが伴うことも
出資を受ける場合、自社の株式を渡すことになるため、将来的に株主総会や取締役会での議決権の割合が変化し、経営者自身の意見が通りにくくなる可能性もあります。
また、経営者が株式を売却してしまう「出口戦略(EXIT)」を出資者が求めるケースもあり、M&AやIPOなど、会社の将来像に関わる決断を迫られる可能性も高いです。
中長期的に、自分の会社をどのように成長させたいのか、経営の主体性や事業の方向性をどうコントロールするのかという点を考えながら、出資を受けるかどうかを検討する必要があります。
融資を受ける際の最大の注意点
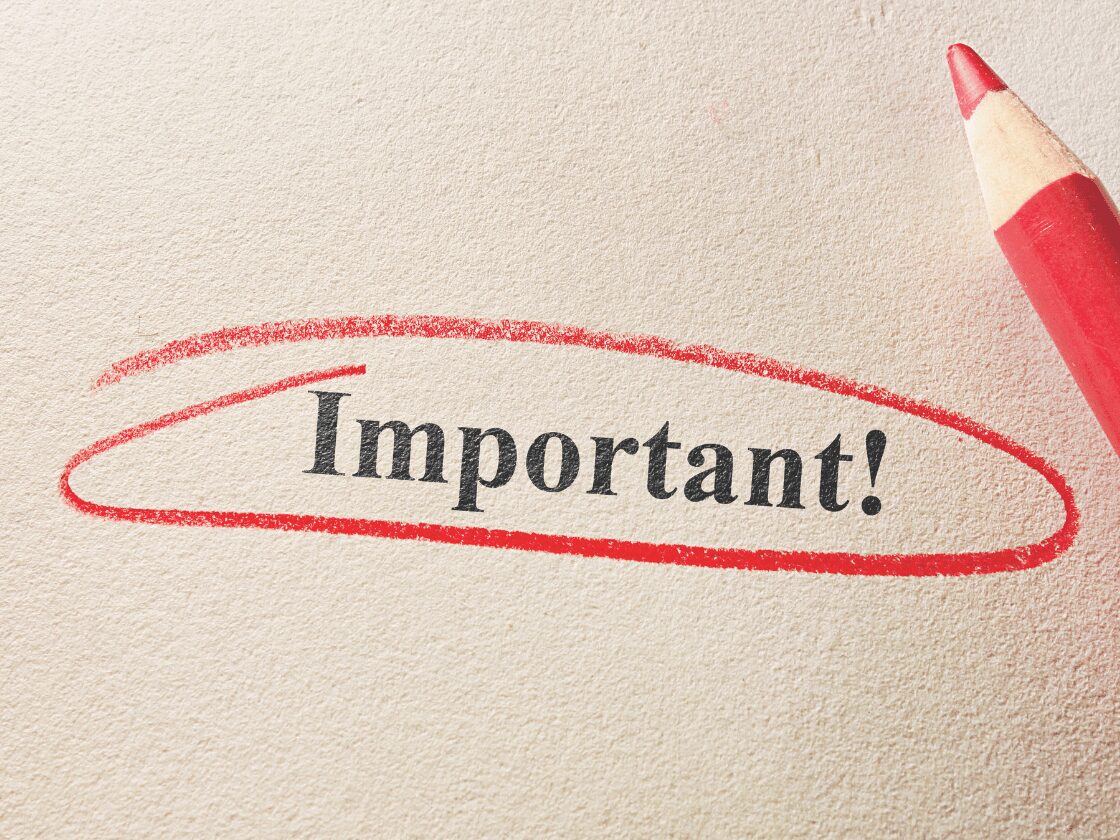
融資を受けるうえで最大の注意点は、「安易に借りて、返済できずに資金繰りに行き詰まるリスク」です。
特に景気の変動や取引先の状況によってキャッシュフローが不安定になる業種(運送・建設・不動産・製造など)では、借りすぎは大きな負担となりかねません。
対策のポイント
- 返済シミュレーションを徹底する
月ごとの売上予測や経費の試算を行い、きちんと返済できる体制があるかを検討する。 - 複数の金融機関と関係を築く
ひとつの銀行だけに依存せず、信金や政府系金融機関などにも相談することで、より条件のよい融資や柔軟な対応を得られる可能性が高まる。 - 融資の目的を明確にする
設備資金や運転資金など、具体的な使い道を明確化しておく。
あいまいな理由では金融機関の信頼を得にくく、また返済計画も立てにくい。
出資を受ける際の最大の注意点

出資を受ける際の最大の注意点は、「経営権をある程度手放すリスク」と「出資者との関係性が複雑になる可能性」です。
大きな資金を得られる反面、出資者へのリターンをどう提供していくか、経営方針をどこまで調整するかなど、合意事項を明確にしておかないとトラブルの元になります。
対策のポイント
- 出資契約書の内容を入念にチェック
株式の持分比率や議決権、役員派遣の有無など、将来の経営に直接影響する条件をしっかりと確認する。 - 経営ビジョンやゴールを共有する
出資者と会社の成長戦略を共有し、将来像について方向性が一致しているかを確認する。ゴールがずれていると揉め事の火種となる。 - Exit(出口戦略)のタイミングを話し合う
ベンチャーキャピタルなどは投資回収を念頭に置いているため、IPOやM&Aなどの出口戦略に対する考え方をすり合わせておく。
スムーズに融資を受けるためのポイント
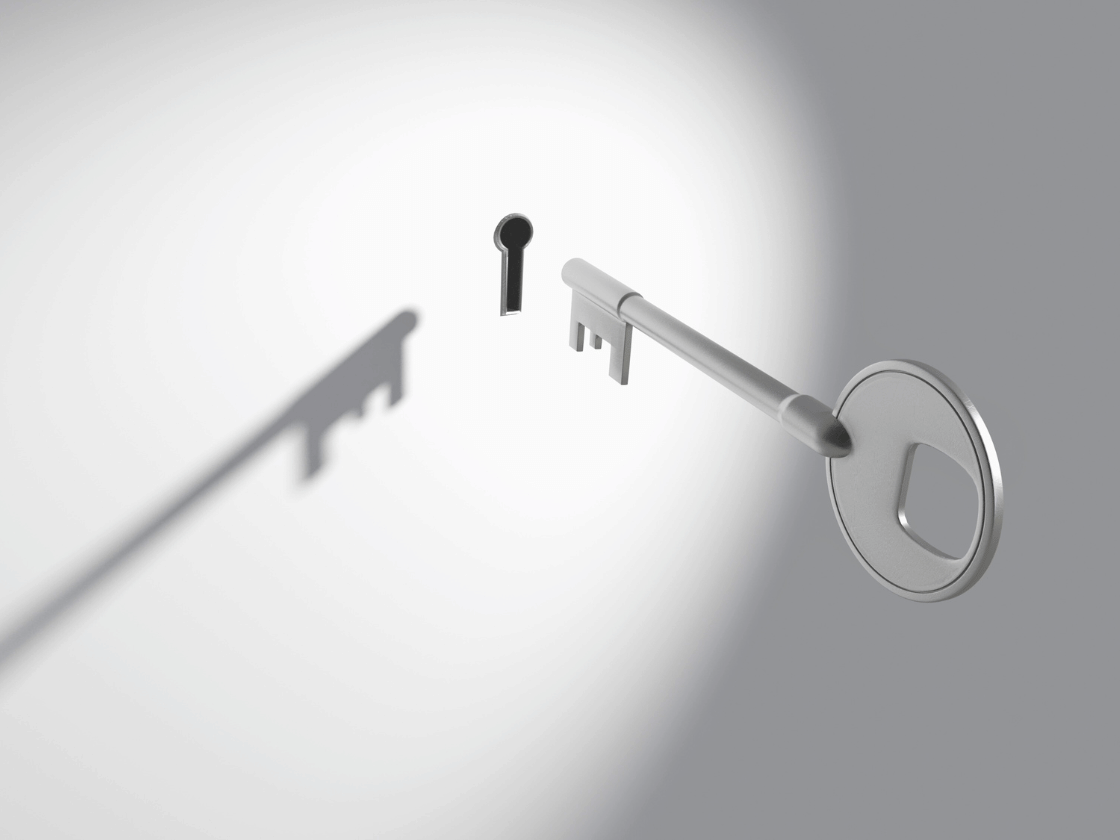
1. 資金使途と返済計画を明確に示す
融資には、多額の設備投資が必要なケースや、新たに人材を採用して組織強化を図りたいケースなど、いろいろな目的があります。
金融機関は「融資したお金がどう使われるか」「返済原資がどこにあるのか」を重視するため、具体的な資金使途と返済計画をしっかりと説明できるようにしましょう。
2. 資金繰り表や事業計画書を丁寧に作成する
資金繰り表や事業計画書の作成は手間がかかりますが、これらの書類は金融機関との信頼関係を築くうえでとても重要です。
根拠のある数字や、リスク対策のシナリオまで盛り込むことで、銀行担当者や支店長に好印象を与えることができます。
- 資金繰り表: 少なくとも1年先までの月次の現金収支をシミュレーションし、支払いや返済をどのタイミングで行うかを見える化する。
- 事業計画書: 今後の事業展開や新規事業の見通し、競合との差別化戦略などをわかりやすくまとめる。
3. 顧問税理士や専門家のサポートを活用する
専門家のサポートをうまく活用することもスムーズな融資獲得には欠かせません。
ただし、顧問税理士が融資調達に詳しくない場合や、金融機関との交渉経験に乏しい場合は、別の専門家やコンサルタントを探すことも検討しましょう。
融資を成功させるには、金融機関の視点に立った説明が大切です。
金融機関が審査時にチェックするポイントや、融資を断る理由などを事前に把握しておくことで、準備の質が高まります。
なお、当社は主に数千万円を超える大口の融資調達を実現するサポートを得意としています。
元銀行の融資審査部出身のコンサルタントが結果にサポートを行い、融資調達を果たします。
初回相談は無料です。
お気軽にご相談ください → 料金はこちら
スムーズに出資を受けるためのポイント

1. 成長ストーリーとビジネスモデルを具体化する
出資者(投資家)は、将来的なリターンを期待して資金を投入します。
そのため、「どんな市場で、どのように成長し、どれほどのリターンを期待できるのか」といったストーリーが重要です。
スタートアップであっても、売上規模や事業拡大の見通しを具体的な数字で示すことで、出資者の信頼を得やすくなります。
2. 投資家との相性を見極める
出資は長期的なパートナーシップを前提とするため、単に資金を出してくれるだけではなく、経営理念や事業ビジョンに共感してくれる投資家であるかどうかを見極めることが大切です。
- ベンチャーキャピタル(VC):
投資回収までの期間が比較的短めに設定されることが多く、成長スピードを求められる。 - 事業会社や戦略投資家:
同業・隣接業界のネットワークや顧客基盤を提供してくれることがある。
長期的支援が得られる場合もある。 - エンジェル投資家:
個人の投資家であることが多く、実業経験や人脈を活かして協力してくれる。
3. 利害関係やExitプランを事前に明示する
出資者との間で、将来的な利益配分やExitプラン(IPOやM&A、株式買取など)を明確にしておくことで、後々のトラブルを防止できます。
出資者は「いつ・どのタイミングでリターンを得るのか?」を気にするので、リスクとリターンをしっかり説明することが求められます。
【まとめ】融資と出資の違いを理解し、計画的に資金調達を実行しよう!
「融資」と「出資」の違いを理解することは、事業をスムーズに成長させるうえで欠かせません。
特に、運送業や建設業、製造業、不動産業など、多額の設備資金が必要な業種や、スタートアップ企業の経営者にとっては、資金調達の選択肢を冷静に検討することが重要です。
- 融資:
返済義務がある代わりに、経営権を手放さずに済む。
安定した経営基盤や実績があれば、比較的安定的に資金を借り入れることも可能。 - 出資:
返済義務はないが、経営権の一部を手放すことになる。
投資家の関与やExit戦略に配慮する必要がある。
それぞれの特徴や注意点を踏まえたうえで、「自社に合った資金調達方法は何か」を検討しましょう。
ときには融資と出資を組み合わせて、リスク分散を図る戦略も有効です。
金融機関だけでなく、投資家とのコミュニケーションも経営者にとっては貴重な経験になります。
最後に、融資や出資のいずれにおいても「事業計画書」の作成が非常に重要です。
なぜ資金が必要なのか、返済・リターンの原資はどこから生まれるのかなど、具体的に示すことで資金調達のハードルは大きく下がります。
顧問税理士や金融コンサルタント、経験豊富な専門家のサポートを活用するなどして、事前の準備を念入りに行いましょう。
事業には常にリスクが付きまといますが、資金調達の方法をしっかり検討し、各ステークホルダーと良好な関係を築くことで、より堅実かつスピーディに成長していくことが可能です。
融資と出資の違いを正しく理解し、計画的に資金調達を実行して、あなたのビジネスを次のステージへ引き上げてください。
お問い合わせはこちら
- メール:muramatsu@honmaru.jp
- お問い合わせフォーム:こちらから
初回のご相談は無料です。
銀行からの融資・資金調達に悩んでいる方は、お気軽にご相談ください。
大口融資調達のご相談はお任せください!
「もっと具体的な融資調達のアドバイスが欲しい」「1億円以上の大口融資を確実に成功させたい」
とお考えなら、ぜひ当社のサポートをご利用ください。
私たちは、1,000万円以上〜最大100億円規模の大口融資調達の豊富なノウハウを持っており、元銀行員の視点から、銀行との交渉や書類作成を徹底的にサポートします。
特に、大口融資の調達においては、細かな計画や銀行への信頼性のアピールが不可欠です。
当社では、銀行融資審査のプロフェッショナルが、企業の財務状況や事業計画をしっかりと分析し、最適な形で銀行へアプローチするお手伝いをいたします。
大口融資を成功させるためのご相談は、お気軽にお問い合わせください。
無料相談も受け付けておりますので、まずはお話をお聞かせください。融資調達の専門家として、あなたの事業の成長を全力でサポートいたします。