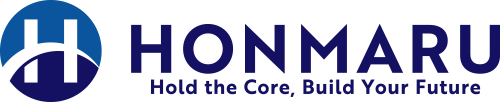- 「節税=融資NG」ではない。
銀行は決算書の表面ではなく、役員報酬や簿外資産など「実質的なキャッシュの強さ」も評価している。 - 大きな利益を出さなくても、
適切な戦略(例:役員報酬・積立・退職金原資など)で実質的な資産を確保し、銀行への情報開示を行えば、高い評価を得られる。 - 銀行担当者によってスキルや理解度はまちまち。
担当者への説明力と、プロフェッショナルな支援が融資成功の鍵。 - 当社の社外CFOサービスを活用すれば、
銀行交渉や財務戦略が大きく改善し、好条件融資を引き出す可能性が高まる。 - 節税・資金調達・銀行との関係構築の3つを両立
させたいなら、ぜひ当社へご相談ください。
この記事は約7分で読めます。
「融資」や「資金調達」を検討している経営者の方から、しばしばこんなご相談を受けます。
「節税に力を入れて法人税を抑えていると、銀行融資の審査が不利になるのでは?」
確かに、節税は決算書上の利益を小さくする行為を伴いがちです。
しかし、実は銀行が評価するポイントは“単に利益が大きいかどうか”だけではありません。
むしろ、役員報酬や簿外資産を活用し、法人税を低く抑えていても、銀行から好条件で融資を引き出している企業は意外に多く存在します。
本記事では、「融資」+「節税」+「注意点」というキーワードを軸に、銀行の評価ポイントとキャッシュ戦略、さらには複数の銀行と信頼関係を築く重要性を詳しく解説していきます。
最後に当社が提供する「社外CFOサービス」についてもご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
大口融資調達のご相談はお任せください!
私たちは、1,000万円以上〜最大100億円規模の大口融資調達の豊富なノウハウを持っており、元銀行員の視点から、銀行との交渉や書類作成を徹底的にサポートします。
特に、大口融資の調達においては、細かな計画や銀行への信頼性のアピールが不可欠です。
当社では、銀行融資審査のプロフェッショナルが、企業の財務状況や事業計画をしっかりと分析し、最適な形で銀行へアプローチするお手伝いをいたします。
大口融資を成功させるためのご相談は、お気軽にお問い合わせください。
問い合わせフォームより相談を受け付けておりますので、まずはお話をお聞かせください。
「節税すると融資を受けにくい」は本当なのか?

節税=決算書上の利益を圧縮する行為
企業が節税に取り組む理由は、「法人税や所得税などの納税額を抑え、手元資金を厚くしたい」という理由が多いでしょう。
たとえば、役員報酬を増やしたり、設備投資を一時償却したり、退職金積立の仕組みを活用したりとさまざまな方法が考えられますが、これらは決算書上の最終利益を下げる形になる場合が多いのは事実です。
銀行は“数字の表面”だけで判断しない
「利益が小さい=返済能力が低い」という単純な図式では、銀行は本来の稼ぐ力を見誤ってしまいます。
最近の銀行は、企業のキャッシュフローや簿外資産、役員報酬の妥当性などをトータルで判断するケースが増えています。
特に、年商3億円~10億円以上あるような中堅・中小企業の場合、一定以上の売上を継続していることや経営者の資金管理能力も評価の対象です。
表面上の利益が小さくても、「本当は儲かっていて、節税で圧縮している」と分かれば、銀行は融資を前向きに検討する余地が十分あります。
銀行担当者のスキル・理解度の差が大きい
とはいえ、銀行担当者のすべてが中小企業の財務・税務に精通しているわけではありません。
経験の浅い担当者や知識不足のケースでは、「利益が低い=融資が難しい」と短絡的に判断する可能性があります。
※私の経験上、全国の銀行員の融資審査スキルはみなさんが思っているよりも遥かに低いです。「決算書を読めない銀行員」がとても多いのです。話が長くなってしまうので割愛しますが、業界の構造上やむを得ないことになってしまっています・・・
したがって、「銀行担当者の視点を補足するように、適切な説明資料を整えたり、別の担当者や支店長へ直接アピールできるルートを作る」ことも大切です。
人事異動などで担当者が入れ替わることも珍しくないため、複数の金融機関や、融資に強いコンサル・税理士と連携しながら進めるのが理想といえます。
「利益ゼロ」に近くても銀行から高評価を得ている実例
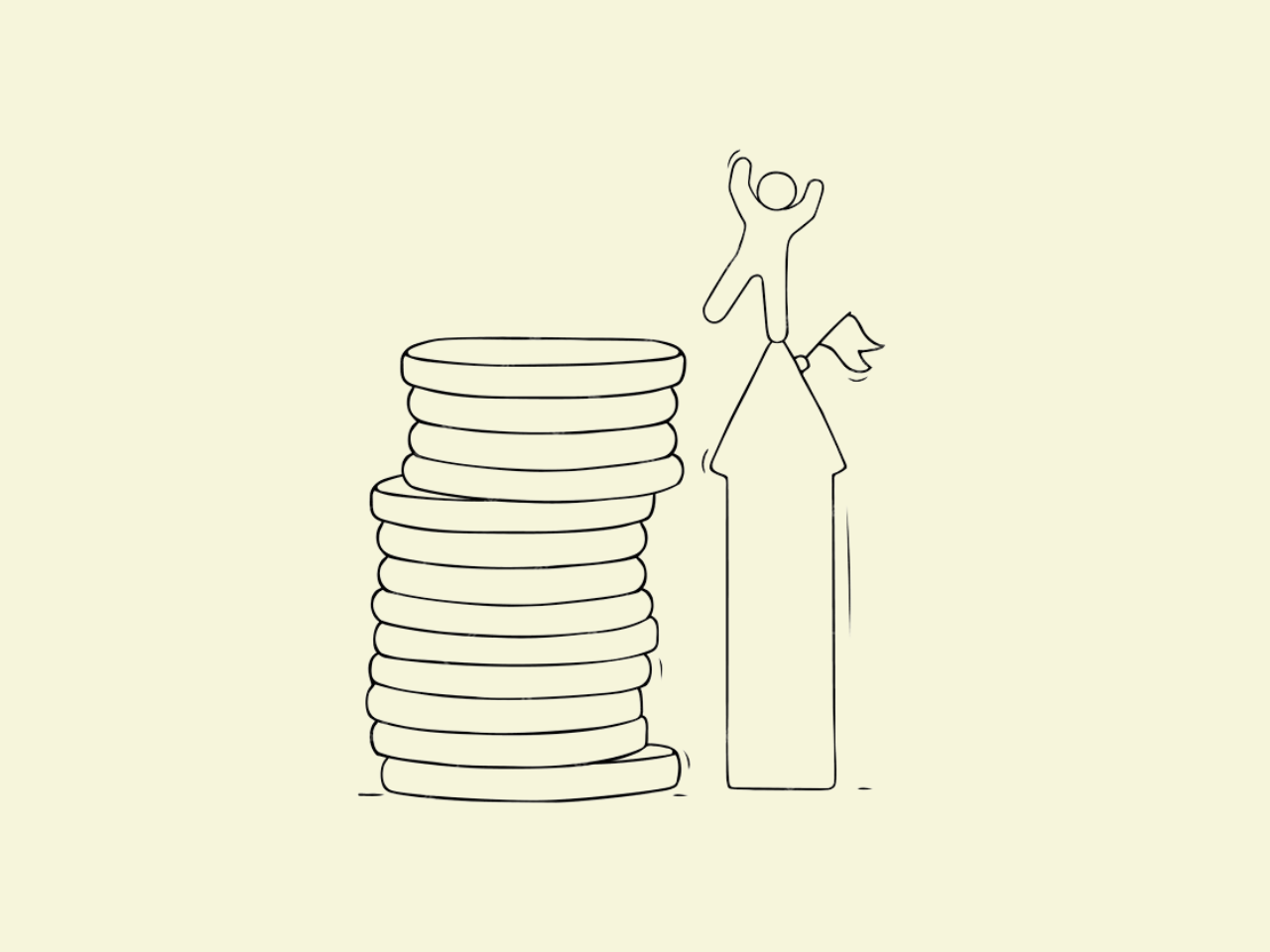
事例:売上7億円、利益150万円でも好条件融資
私がリスペクトするある著名な税理士先生が紹介する事例で、有名なものにこんな会社があります。
- 年商:7億円(創業20年)
- 累計利益:20年で3,000万円(1年平均150万円の利益)
- 表面だけ見ると「ほとんど利益を出していない」ようにも見えますが、実際には銀行から好条件で融資を受け続けています。
なぜでしょうか?
理由1:役員報酬をかなり多く取っている
この会社では、役員が2名で年間8,000万円という高額な報酬を設定しています。
決算書上は利益が少なくなりますが、実際は経営者個人に多くのキャッシュが残っているわけです。
銀行は「会社の経営実態を正しく把握しよう」とするとき、役員報酬の大きさ=本当は利益が出ている証拠と捉えることもあります。
仮に役員報酬を適宜コントロールすれば、会社に利益を残すことも可能ですし、それだけ返済能力の余力があると判断されるのです。
理由2:簿外資産(将来返ってくる資金)がある
もうひとつのポイントは、決算書には載っていないが、数年後に返ってくる資産(簿外資産)を保有している点です。
これは「隠している」というより、退職金積立や生命保険の解約返戻金など、経費として処理しながら将来的にキャッシュが手元に戻る仕組みを指します。
銀行は、こうした資産があることを把握すると、「いざというときは返戻金を活用して返済に充てられる可能性がある」と考え、評価を高めることがあります。
法人税を低く抑えながら“キャッシュリッチ”に
利益を大きく出さなくても、役員報酬や積立を戦略的に使い、個人や将来の会社にキャッシュを蓄える形を取ることが可能です。
これにより、当面の法人税は低く抑えながら、いざというときの返済原資を確保できるわけです。
銀行担当者にきちんと説明できれば、「会社の実力は十分ある」と理解してもらい、結果的に高い評価を得ることができるのです。
役員報酬を高く設定するメリット・デメリット
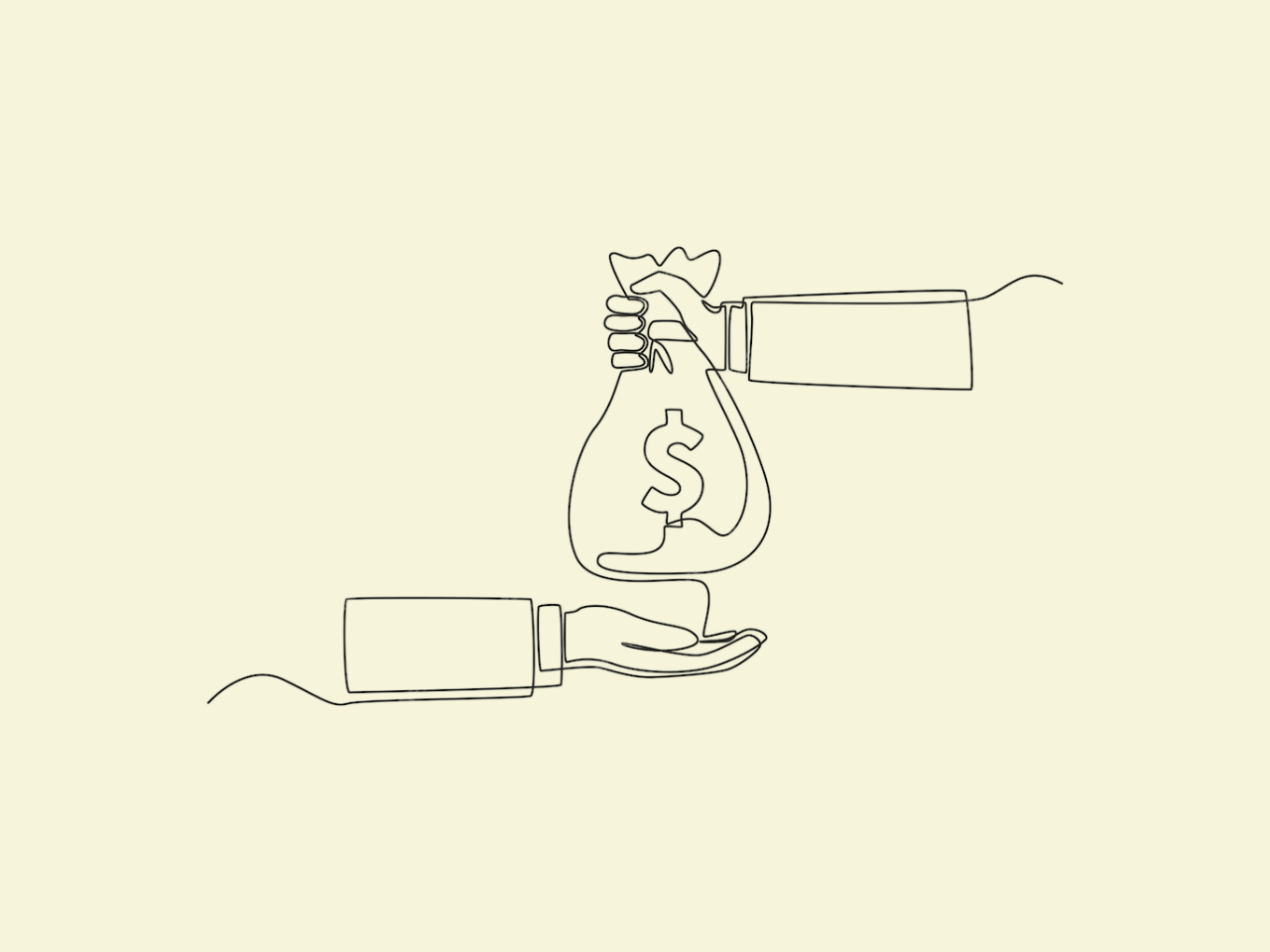
先の事例でも分かるように、役員報酬を多めに取ることが決して悪いわけではありません。
しかし、銀行融資や資金調達を見据えた場合、メリットだけでなくデメリットや注意点も存在します。
役員報酬を高く設定するメリット
- 個人資産が増える
役員報酬を多めに設定することで、経営者個人が潤沢な資産を形成しやすく、万が一のときに会社へ貸し付けるなど柔軟な対応が可能となります。 - 法人税の圧縮
役員報酬は法人にとって経費扱いなので、利益を適度に圧縮し、納税額を低減できます。 - 銀行評価にも好影響
一見、利益が出ていないように見えても、実際は役員報酬として支払う余力がある=「稼ぐ力」を持っていると銀行が判断する場合があります。ここが意外と知られていないポイントです。
役員報酬を高く設定するデメリット・注意点
- 社会保険料や個人の所得税が高くなる
役員報酬を高く設定すれば、その分、個人の所得税率や社会保険料が上がります。結果、個人の可処分所得が思ったほど増えないケースもあるため、トータルコストをシミュレーションする必要があります。 - 無計画に増やすと銀行側に疑問を持たれる可能性
毎年のように役員報酬を大きく上下させたり、会社の売上にそぐわない高額報酬を設定すると、銀行側も「何か無理をしているのでは?」と不信感を抱くかもしれません。 - 担当者の理解不足リスク
前述のとおり、担当者のスキルレベルによっては「利益率が低い会社」とネガティブに評価されてしまう恐れも。
きちんと経営実態を説明できる資料や、サポートしてくれる専門家が必要です。
参考記事:複数銀行に同時打診して好条件を引き出す!事業性融資の「攻略法」と「失敗回避ポイント」
\ 複数の銀行を比較・調整して最適な融資形態を探るなら /
お問い合わせフォームから、どんなお悩みでもお気軽にご相談ください!
節税&大口融資の両立を図るためのポイント

銀行融資や資金調達を成功させるうえで、節税とキャッシュのバランスは非常に重要です。
以下のポイントを押さえておくと、よりスムーズに融資交渉を進めることができます。
簿外資産や各種積立の情報をオープンにする
たとえば、
- 退職給与引当(役員退職金積立の保険)
- 生命保険の解約返戻金
- 契約内容によって戻ってくる積立金
など、「将来返ってくるお金」や「手元に戻せる可能性のある資産」を整理し、銀行へ説明できるようにしておきましょう。
決算書だけでは分からない資産状況を正しく伝えることで、「表面上の利益が小さいのは節税だが、実際にはキャッシュ面で余力がある」と示せます。
事業計画書や資金繰り表をしっかり作る
「役員報酬を高く取っています」や「節税で利益を圧縮しています」という説明だけでは、銀行担当者が納得しきれない場合もあります。
そこで、事業計画書や月次の資金繰り表を提示することが有効です。
- 3〜5年先の収支予測
- 設備投資や営業戦略、取引先拡大計画
- 資金の使途と返済原資の明確化
これらを具体的に示すことで、担当者が「この会社なら返済してくれそうだ」と安心できます。
特に、地域金融機関(地方銀行・信用金庫)では、経営者の人物像やビジョンを重視するケースが多いため、面談時のプレゼンも重要です。
参考記事:【融資で3000万円・資金調達したい!】大口融資調達のプロが確実に資金調達を成功させるポイントを伝授!
銀行担当者との関係構築&複数の金融機関を検討
銀行の担当者は異動がつきもの。優秀な担当者と良い関係を築いていても、すぐに部署が変わることが珍しくありません。
そのため、複数の金融機関と取引を持ち、担当者レベルで情報共有できる体制を整えておくと安心です。
- 「A銀行の担当者とは、節税や役員報酬の話まで深く共有できているが、B銀行の担当者にはあまり説明できていない」
- 「C信用金庫でも別の視点のアドバイスをもらえるかもしれない」
こうした形で複数行の見積もりを取りながら交渉を進めることで、融資の条件や金利を比較検討しやすくなるだけでなく、担当者による“当たり外れ”のリスクを分散できます。
参考記事:複数銀行に同時打診して好条件を引き出す!事業性融資の「攻略法」と「失敗回避ポイント」
社外CFOサービスを活用する
当社では、「社外CFOサービス(Chief Finacial Officer:外部の最高財務責任者)」を通じて、企業と銀行の橋渡しや財務戦略のコンサルティングを行っています。
詳しくはこちらの詳細ブログをご覧ください。(参考記事:【徹底解説】銀行融資に特化した社外CFOサービスとは?メリットと導入の流れ)
- 複数の金融機関とのパイプを活用し、経営者をサポート
- 決算書のブラッシュアップや役員報酬設定のアドバイス
- 銀行交渉・融資面談で経営者に代わってプレゼン資料を作成
「節税はしたい、でも銀行融資も有利に進めたい」という企業にとって、外部の視点で財務全般を最適化することは大きなメリットがあります。
\ 計画書の作成に不安がある場合は専門家にお任せ /
当社では事業計画書のテンプレート提供から個別コンサルティングまで行っています。
詳しくはこちら
【まとめ】銀行融資で大口資金調達を目指すなら「節税+複数銀行との関係構築」を

「節税をすると銀行融資が不利になる」という噂は、決算書の表面的な利益しか見ない銀行担当者が一定数いるからなのかもしれません。
実際には、役員報酬や簿外資産を活用して法人税を低く抑えながら、銀行から高い評価を得ている企業も数多く存在します。
一番のカギは、銀行担当者との関係性と、複数の金融機関との付き合い方です。
同じ書類でも、理解度の高い担当者なら「この会社はしっかりキャッシュを残している」と前向きに捉える一方、知識不足の担当者だと「利益が低いから危ない企業」と思われる可能性があります。
社外CFOサービスで銀行交渉を変える
当社の「社外CFOサービス(外部の最高財務責任者)」では、銀行との折衝を強力にバックアップします。
複数の銀行を比較しながら、融資条件や金利をより有利に引き出す交渉をサポートし、企業の“真の財務状況”を正しく伝えることで、銀行との信頼関係を構築します。
- 決算書や試算表の適切な見せ方
- 役員報酬の戦略的な設定
- 簿外資産・退職金積立の内容をわかりやすくまとめる
- 事業計画書の策定や面談同行
こうした総合的なサポートを受けることで、今までの銀行取引とは見違える成果が得られることも少なくありません。
詳しくは、こちらのブログで詳しく解説しています。
当社へのご相談はお気軽に
- 年商3億円以上の企業で、複数の銀行から大口融資を引き出したい
- 顧問税理士が融資に詳しくなく、相談相手に困っている
- 役員報酬や簿外資産を活かした節税・財務戦略を確立したい
このような課題をお持ちの経営者の方は、ぜひ当社大口融資調達サポートへお問い合わせください。
中小企業を中心に、銀行融資・資金調達・財務戦略に関する幅広い実績を持っています。
【この記事のポイントおさらい】
- 節税=融資NGではない:表面的な利益が小さくても、銀行はキャッシュフローや簿外資産を総合的に見る。
- 役員報酬は高くてもOK:適切な根拠があれば、銀行側に“稼ぐ力”の証明になる場合がある。
- 複数の銀行と取引する:担当者のスキルや融資姿勢はまちまち。最低2〜3行は検討しよう。
- 社外CFOサービスで一気に交渉力UP:プロの目線で決算書や事業計画を整え、銀行へ正しくアピール。
- 当社にご相談ください:設立5年以上、年商3億円以上など、大口融資調達を考える企業には最適なサポートを提供。
当社では、銀行融資でお悩みの経営者に対して、税務や節税とのバランスを踏まえた財務戦略をトータルで支援しています。
ぜひお気軽にお問い合わせいただき、“節税しながらも有利な銀行融資”を実現させましょう。
お問い合わせはこちら
- メール:muramatsu@honmaru.jp
- お問い合わせフォーム:こちらから


1億円以上の難易度の高い
大口の融資調達に対応!
元大手銀行×融資審査部にて2,000社以上の融資に携わった
プロがサポート!
【毎月5組限定・ご相談受付】